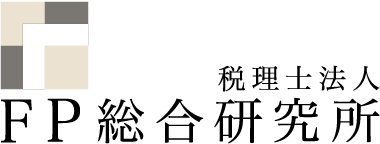【No183】ジョイント・テナンシーと税金
先日、医師であるご夫婦が米国の不動産を購入しようと検討しており、その際に先方(不動産を仲介する弁護士)から『ジョイント・テナンシー』の説明を受け、その税務についてのご相談がありました。
米国の不動産の購入おいて、ジョイント・テナンシーはよく使われるもので、このジョイント・テナンシーとは、簡単に考えると共有不動産のことです。ただ、細かくみていくと日本の共有の考え方とも異なり、税務面において注意すべき点があります。
まずは、そのジョイント・テナンシーについて確認したいと思います。
1.ジョイント・テナンシーとは(日本における「共有」との違い)
日本にも不動産などにおいて、夫婦で「共有」という形で所有する形態はあります。共有の場合にはその持分が決まっていて、たとえば、その不動産を売却するときには、共有者全員の承諾がないとその不動産自体の売却はできません(もちろん、共有の持分のみを売却することは可能)。
また、その共有者が死亡した場合には、原則的には、その共有者の相続人がその持分を承継することになります。
では、米国におけるジョイント・テナンシーと、どのように異なるのでしょうか。
まず、米国においては2人以上の者が財産を所有する形態として、
①合有財産権(Joint Tenancy)
②共有財産権(Tenancy in Common)
③夫婦合有財産権(Tenancy by Entirety)
④夫婦共有財産権(Community Property)という制度があるそうです。
このなかで①と③の「合有」というものが、ジョイント・テナンシーとなります。
そして、合有権とは、
イ:同一の財産に関する同一の譲渡行為によって(unity of title)
ロ:2名以上の者が同一の時に始期を有する(unity of time)
ハ:同一の権利(unity of interest)を
二:共同所有する(unity of possession)
という、4つのunity(同一性の要件)を備えた財産権となるそうです。
そして、その特徴は、合有権者の1人が死亡するとその持分は他の合有権者に移転(死亡者の権利が消滅する)し、合有権者には任意にも強制にも分配する権利は与えられておらず、これは遺言によっても変更することはできないというところにあります。
この特徴のために、米国などでは、相続が発生した場合における煩雑な『検認手続き=Probate』を回避する方法として、広く活用されているようです。
また、この特徴のために日本における課税の捉え方の問題も生じています。
2.ジョイント・テナンシーと税金
ジョイント・テナンシー制度は、日本には存在しない法制度です。日本に無い制度だから日本の税法が適用されないということでは、課税の公平性が保たれないので、日本の税制と照らし合わせてどのように解釈し適用するかが問題となります。この点を判例等により現状の解釈を確認したいと思います。
ジョイント・テナンシーにて不動産を取得した事例
【判例】平成29年10月19日名古屋地裁判決(納税者の請求は棄却,確定)
【事実関係】
①平成19年に米国カリフォルニア州所在のコンドミニアム取得(当該不動産とします)
②当該不動産の購入代金は夫が負担
③当該不動産を夫妻でジョイント・テナンツとして登記
④当該不動産の取得に対しては何ら記載せずに贈与税の申告書(他の贈与があり)を提出
⑤税務署調査により、妻は夫から当該不動産の2分の1相当の利益を得たとみなし、相続税法9条により更正処分
⑨異議申立て、国税不服審判所を経て裁判となる。
【裁判所判断】
夫婦は、ジョイント・テナンシーの要件を満たす方法により当該不動産を購入し、当該不動産のジョイント・テナンツとして登記したものであり、それぞれ2分の1の持分を有するための当該不動産の取得資金を全額夫が負担していることからすれば、妻は対価を支払うことなく当該不動産の2分の1相当の経済的利益を得たというべきであるから、贈与税の課税の基礎となるみなし贈与があったと認められる。
【相続税法9条】※一部要約
第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす。
【コメント】
ジョイント・テナンシー制度は日本には存在しないものですが、相続税法9条にあるように、『対価を支払わずに利益を受けた場合には贈与により取得したものとみなす』規定により贈与税が課税されるので注意が必要です。
(文責:税理士法人FP総合研究所)